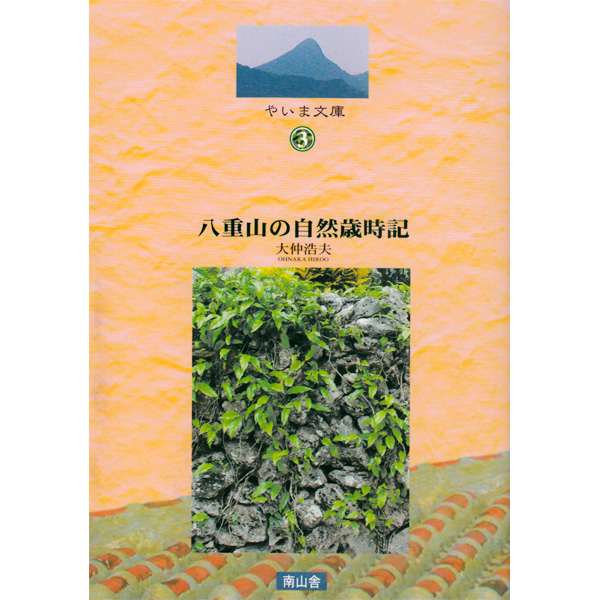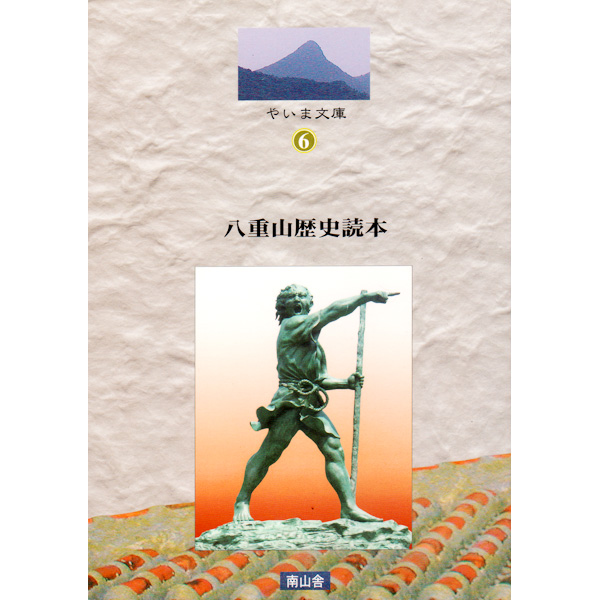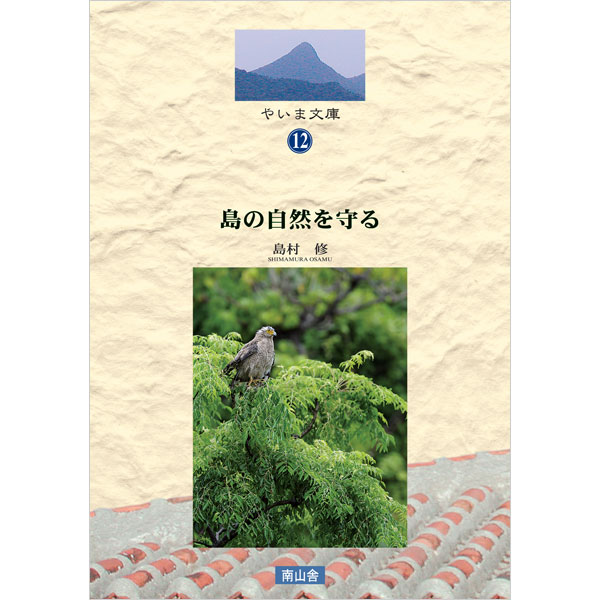移民の歴史からたどる「八重山合衆国」形成史
近世以降、強制移住や開拓移民の入植などで、「合衆国」とも呼ばれる独自の社会を形成してきた八重山。その移民の歴史を総合的に検証。

コンテンツ
序 文 ― 歴史のタテ糸とヨコ糸 ―
移民前史としての近世寄人制度
第Ⅰ部「八重山合衆国」形成史
はじめに
明治期
一、「廃藩のサムレー」の栄光と挫折― 首里・那覇士族のシーナ原開墾 ―
二、製糖で四国から大量移民― 中川虎之助の名蔵開墾 ―
三、出稼ぎ漁から定住へ― 海の遊牧民・糸満漁民の進出 ―
四、商店街から製造業まで― 大和・那覇寄留商人の商業進出 ―
大正期
一、景気支えたカツオ漁業― 造船・鉄工所にも波及 ―
二、過酷な坑内労働の下で― 西表炭坑の本土・台湾人坑夫 ―
昭和期
一、パイン産業と水牛を導入― 台湾人農業移民の名蔵入植 ―
二、戦争で難渋した沖縄振興計画移民― 開南・川原・南風見の入植開墾 ―
戦後期
一、島の地図塗り替えた集団入植― 背景に戦後の人口急増と米軍基地建設 ―
第Ⅱ部「八重山合衆国」を生きる― 三木専太郎にみる近代八重山 ―
一、台湾から八重山へ
四国から日露戦争に従軍
農業移民として台湾へ
石垣町登野城に「山菱製材所」を設立
表面化した台湾航路運賃問題
二、大正・昭和の寄留民群像
活発な大正期の石垣島
鶴亀堂の三島庄太郎
さまざまな寄留者たち
台湾人の入植と排斥運動
「無名会」と主張する寄留者たち
出直し選挙で町会議員に
三、戦時体制下を生きる
長男・義行、鶴亀堂の清子と結婚
戦時体制下の警防団長に
三島家の台湾移住
清子と子供たちの台湾疎開
戦争マラリア、そして敗戦
四、戦後の開拓事業
伊野田開墾
途半ば、義行の他界
息子の弔い合戦
農場の売却と専太郎の死
「八重山合衆国」略年譜
あとがき
著者
 三木 健(みき たけし)
三木 健(みき たけし)
1940年、沖縄石垣島生まれ。八重山高校、明治大学政経学部卒業後、1965年琉球新報社入社(東京支社報道部記者)。同社編集局政経部長、取締役編集局長を経て、現在常務取締役。主な著書に「西表炭坑概史」、「八重山近代民衆史」、「八重山研究の人々」、「リゾート開発」、「沖縄ひと紀行」などがある。
書評 琉球新報 ~近代史のきめ細かな絵巻物~
多数の著書を持つ三木氏は、本書にどのような思いをこめたのであろうか。書名には合衆国や系譜という魅力的な字が躍る。『八重山合衆国』とは、新鮮で広域的な着想だ。地域と移民(移動民、移住民)の交流を豊かに連想させる。
本書は八重山地域の近代史を基本ベースにしながら、三木家三代の家族史を系譜の中で、その関係史の織り成す造形の布を検証する野心的な労作となっている。近代史の縦糸と横糸のきめ細かな絵巻物である。
近代史を人々の息遣いや皮膚感覚を通して、自分史、家族史、地域史を統合的に再構成し、バランスを保って記述する。新しい学問の手法を模索しているかのようである。八重山地域の近代の個性は、それを可能にする豊穣の基盤をもっているのであろうか。
本書は、二部構成になっている。第一部が「八重山合衆国」形成史で、明治期、大正期、昭和期、戦後期に分けて、移住の変遷を産業の発展をさまざまな影響を受けつつ展開する様相を冷静に描く。文中の病魔マラリアと格闘し敗北する姿は、痛ましい。
第二部は「八重山合衆国」を生きる「三木専太郎に見る近代八重山」となっている。著者は、祖父の人柄の中に、合衆国の原質を見いだしたのかもしれない。
人間描写の筆遣いに学ぶのが多いであろう。確かに、地域と移住者、寄留民、入植者には、予定調和の原理のみが働くとも限らない。利害関係をめぐっては、対立、摩擦、闘争もある。
合理的な構想は、新たな次元で調和、融合、和解を必要とする。その論理と人格を備えた人物として、著者の三木氏は、祖父の専太郎を選択し登場させる。
時代が生んだ魅力溢れる人物で、明治の日露戦争にも従軍し、奉天会戦にも参加している。百数十枚の奉天会戦写真を見たが、そこに写る専太郎に会えたような叙述が絶妙でいい。
随所に収録された貴重な写真は臨場感を高め、大いに理解を助ける。歴史は自らに学ぶという視点を示唆する好著だ。
2010年7月4日付『琉球新報』
我部政男(山梨学院大学名誉教授)
書評 八重山毎日新聞
「八重山合衆国」とは、元もと住んでいた人たちに加えて出身地を異にする多くの人たちが共生し、八重山社会をつくり上げていることを指す俗称だ。「しかも八重山らしさを失うことなく、その社会と文化をつくり上げてきた。あるいは、その調和そのものが八重山社会の特徴だ、と言えなくもない」(著者)のである。
著者はこの「八重山合衆国」の形成と時代背景について新聞資料などを丹念にたどりつつ、独自の視点、新しい切り口によって検証していく。
本書は第Ⅰ部「『八重山合衆国』形成史」と第Ⅱ部「『八重山合衆国』を生きる―三木専太郎にみる近代八重山―」の2部で構成され、公的な領域と私的な領域(著者)から複眼的に叙述される。
第Ⅰ部では移民前史として、近世的寄人制度の象徴ともいえる野底マーペーの伝説から書き起し、「近世期の寄人制度による強制移住の歴史が八重山に移民地の風土を醸成」したと述べる。こうした著者の見方は八重山の近世・近代・現代の歴史をひも解けば十分に納得できるものである。
本論は明治・大正・昭和・戦後の4期に分けて考察される。明治期では首里・那覇の廃藩士族たちのシーナ原開墾と挫折。徳島県の糖業家・中川虎之助の名蔵開墾。糸満漁民の進出と定着による水産界の活気。のちに「あやぱにモール」(現在はユーグレナモールと改称)となるハマクヤー(浜小屋)を形成するようになる大和・那覇の寄留民の商業進出が取りあげられる。
近代沖縄における寄留商人たちの果した役割については功罪両面が指摘されている。その中で、沖縄の民衆の血と汗の成果を収奪して中央に送り込んだといわれる負の面について、著者は全体的には認めつつも、「八重山に関していえば、(中略)一部の大金持ちは別として、農業移民で入植した人たちが、それに失敗してやむなく商売を始めた、といったケースも多」いととらえ、今後の検証のさらなる必要性を述べる。
大正期ではカツオ漁業の盛況と利益をめぐる植民地的構図、造船・鉄工所の出現、西表炭鉱における囚人労働や台湾坑夫の悲惨な実態を浮かびあがらせる。
昭和期ではパイン産業と水牛の導入の経緯、それをもたらした台湾人農業移民の名蔵入植と地元民との間に生じた対立や差別の問題、開南・川原・南風見への沖縄振興計画移民の難渋した様子が取りあげられる。
戦後期では1946(昭和22)年の宮古島から西表島住吉地区への移住を皮切りにはじまった沖縄本島など各地からの自由移民、計画移民が取りあげられる。
著者はこの計画の背景について、戦後の外地引き揚げなどによる人口増があったこと、基地拡大のために土地を強制収用した米軍が軍用地問題の解決策として、農民の代替農地を確保するために、南米ボリビア移民と併せて八重山開拓移民を考え出したことを指摘する。「基地問題と八重山開拓移住は、密接な関係」にあったのである(著者)。
第Ⅱ部は、香川県高松出身の三木(旧姓・前田)専太郎というひとりの人物が八重山という異郷の地に定着していく様子を通して、八重山の近代史を考えていく。
三木専太郎は、日露戦争後の不況の中で台湾、石垣島と移住を重ね、製材所を開設し、さらに長男、妻も呼び寄せて定住し、やがて経済界の大きな存在となり、町会議員にもなる。石垣島最後の空襲で妻・ヤエを失い、戦後はジャングル同様の伊野田開墾に力を注いだ長男・義行を病いで亡くすなど不幸にも見舞われたが、専太郎は息子の死を無駄にしないために再び伊野田開墾をはじめ、三木農場を経営したという。専太郎が波乱に満ちた81年の生涯を閉じたのは、農場を手放したあとの1961(昭和36)年1月のことである。
三木専太郎の歴史はいわば三木家の歴史でもあった。同時に他の入植者や移住してきた人たちの歴史をも象徴するものである。だからこそ「専太郎の生涯は、台湾、寄留民社会、戦争、開墾、と近代八重山のキーワードと深く関わりを持ち」、「『八重山合衆国を生きる』というにふさわしい。」のである(序文)。
三木専太郎は実は著者の祖父にあたる人物だ。著者の筆致は抑制のきいた客観的なものだが、それでも著者が、なぜ第Ⅱ部を書かねばならなかったのかという心情がよく伝わってくる。
八重山の近代史は、時の国家政策や戦争、経済不況に翻弄され、マラリアや自然災害などを克服する歴史でもあった。そういう状況の中で地元民も県内外の移住者も数多くの艱難辛苦を乗り越え、「『八重山合衆国』の一員として、新しい歴史をつくった」(あとがき)。
著者は、「戦後の大規模な集団移民は、集団の構成そのものが沖縄本島や宮古、そして地元というように混成であった。(中略)したがって、お互いの文化や独自性を認め合い協調していかなければ生きていけなかった。入植当初は摩擦や戸惑いもあったに違いないが、それは次第に克服されたのではないか。」(戦後期)と述べ、宮古からの入植者二世である西表島住吉の出身者が立候補した2008年の竹富町長選挙を象徴的な出来事としてあげる。
「もはや『出自』や人種が問題ではなく、その人の人格や、思想が問われることを示している。私たちはそこに未来に生きる知恵を見いだすであろう。」(あとがき)。著者はこう述べたうえで要旨次のように付け加える。タテ糸(伝統的社会)を強くして、ヨコ糸(外からのインパクト)を包み込むだけの力をもたねばならない。ヨコ糸ばかりが強くなるとバランスが崩れ、布(八重山の歴史)は生命力を失うだろう、と(あとがき)。
八重山の「合衆国」化がさらに進み、価値観も複雑多様化の度合いを深めている現在、八重山(人)のアイデンティティや将来を考えるうえで、本書は多くの示唆を与えてくれるはずだ。
2010年6月6日付『八重山毎日新聞』
砂川哲雄(八重山文化研究会会員)
書評 八重山毎日新聞 ~歴史の闇を照射する名著~
「八重山合衆国」という呼称がまず珍しいが、八重山ではかなり以前からその言葉は具体性を持っている。そうであればこその書名であり、その名の由来、系譜を整理してみようというのが著者の根本的動機である。それはまた著者の祖父や父が八重山以外(香川県高松)の出自を持ち、しかし著者本人は八重山で生まれ育ち、ふるさとは八重山以外にないというアンビバレントな感情にも根差している。
名著である。著者はさまざまな資料を渉猟し、よくその系譜を探り得ている。そしてその探求が先鋭かつ誠実であったが故に本書は著者本来の意図を大きく超えて歴史の闇を照射している。名著であるゆえんである。
その闇とは何か。一言で言えば、八重山は常に外界の問題群のはけ口としてのみ利用される存在にすぎなかったという実態である。つまり蔡温の昔は王府を支える農業奴隷であり、明治以降は権力によってある人々に払い下げられた広大な開墾地であり、沖縄本島の貧民の行き先地であり、また日本各地の一旗組の流浪地であった。その最も典型的な例は、戦後米政府により風土病マラリアの撲滅が図られ、地元の医師や住民の全面的協力によってそれは成功したが、その真の目的は沖縄本島において銃剣とブルドーザーによって土地を奪い取られた人々の送り先を確保するためであった事実である。
八重山はそれらの人々を受け入れてきたが、なぜそれが可能であったか、そして外側から来た人々がどのように八重山になじみ八重山にいかなる刺激を与えてきたかが本書後半において著者・三木家三代の変遷を例にとって語られる。
「八重山の伝統的社会をタテ糸とし横糸としての外からのインパクトが組み合わさって調和のとれた模様が織りあげられている」と著者は結論づけるが、それはやや楽観的すぎるのではないか。明示的ではないにせよ「八重山合衆国」とは権力と資本の欲望に沿った八重山社会の破壊と再構成であるのかもしれないのだから。
2010年7月31日付『沖縄タイムス』
八重洋一郎(詩人)