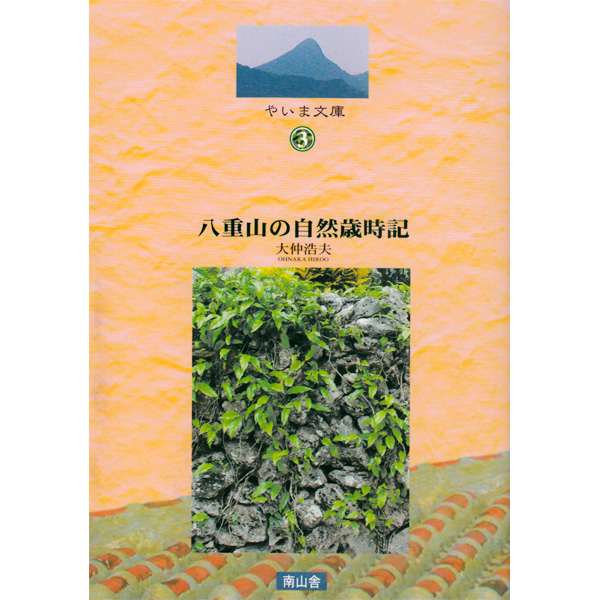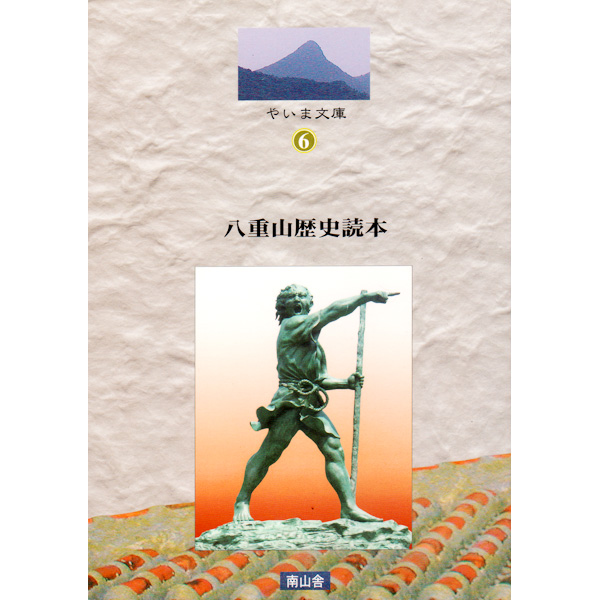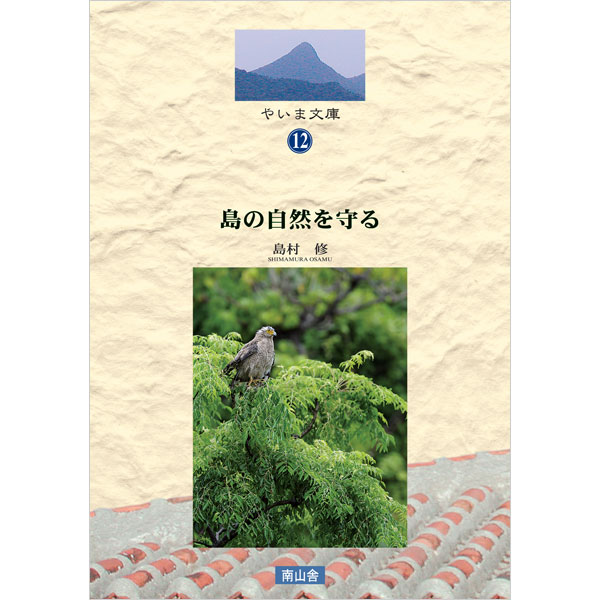- 八重山の社会と文化
▼ 商品説明の続きを見る ▼
価格:1,980円(本体 1,800円、税 180円)
[ポイント還元 19ポイント~]
本について
NPO現代の理論・社会フォーラム 古川 純 編仕様:B6判 ソフトカバー 292ページ
発行:南山舎
送料について
送料は全国一律198円になります。複数購入の場合、計量し一番お安い送料で改めてご案内させていただきます。
[代引きの場合]
ゆうメールにて発送致します。1冊のみご注文の場合、送料は全国一律310円になります。
手数料について
代引きの場合は530円が、コンビニ払の場合は410円が加算されます。予めご了承ください。 他にもこんな商品があります
-
島の歳時記価格:1,980円(本体 1,800円、税 180円)完 売
-
台湾疎開「琉球難民」の1年11カ月価格:2,530円(本体 2,300円、税 230円)
-
潮を開く舟サバニ価格:1,815円(本体 1,650円、税 165円)
-
マラリア撲滅への挑戦者たち価格:1,980円(本体 1,800円、税 180円)
-
よみがえるドゥナン価格:2,090円(本体 1,900円、税 190円)
-
八重山風土記価格:1,980円(本体 1,800円、税 180円)
-
与那国台湾往来記 「国境」に暮す人々価格:2,530円(本体 2,300円、税 230円)
-
八重山の自然歳時記価格:1,540円(本体 1,400円、税 140円)
-
八重山研究の歴史価格:2,068円(本体 1,880円、税 188円)
-
八重山歴史読本価格:2,090円(本体 1,900円、税 190円)
-
島の自然を守る価格:2,090円(本体 1,900円、税 190円)
-
「八重山合衆国」の系譜価格:2,090円(本体 1,900円、税 190円)